業務平準化とは|重要視される理由や進めるためのステップを解説
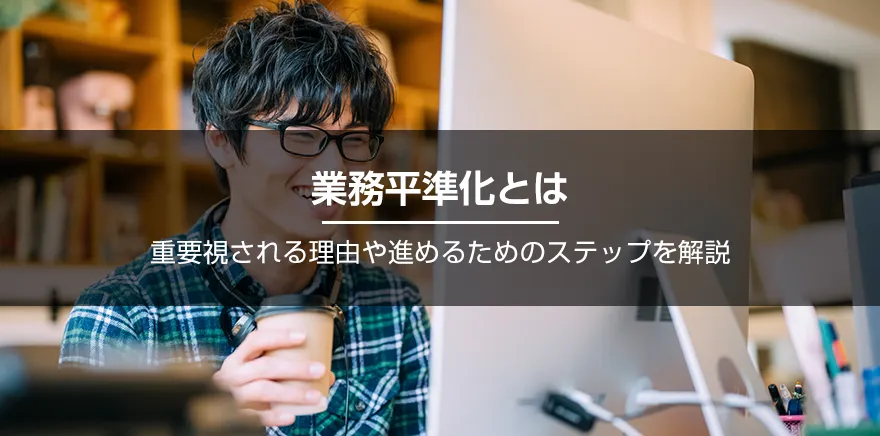
「業務のムラが激しくて、忙しい日と暇な日の差が大きい」「一部の従業員に仕事が集中している」といった課題に直面している企業は少なくありません。こうした状況を解決するための手法として有効とされているのが「業務平準化」です。
業務平準化とは、業務量や作業内容を均等に分散し、特定の人や時期に業務負荷が集中しないようにする取り組みを指します。今回は、業務平準化の意味や重要視される理由、実践に向けた手順を丁寧に解説します。
業務平準化とは

「業務平準化」とは、業務量や作業負荷の偏りを解消し、業務の均一化を図る取り組みです。「平準化」という言葉には、バラつきのある状態を整えて均等にするという意味があります。
具体的には、繁忙期と閑散期で業務量に大きな差がある場合や、特定の担当者に業務が集中しているケースにおいて、業務の見直しや再配分を行い、負荷のバランスを整えていきます。
このように業務平準化を進めることで、チーム全体の生産性向上に加え、属人化の解消や業務リスクの軽減も期待できます。
業務標準化との違い
「業務平準化」と混同されやすい言葉に「業務標準化」がありますが、それぞれ目的や取り組みの内容が異なります。
業務平準化は、主に業務量や作業負荷の「量的なバランス」を整えることを目的としています。
一方、業務標準化は、作業の進め方や手順、ルールなどを統一し、品質の安定や効率化を図る「手法の統一」が主な目的です。
つまり、平準化は「誰がどれだけの仕事をするか」の偏りを解消するためのアプローチであり、標準化は「どうやってその仕事をするか」を明確にするためのものです。
両者を合わせて進めることで、より健全な業務運営が可能になります。
業務平準化が重要視される理由

現代のビジネス環境は、変化が激しく複雑化しています。その中でチームが安定して高いパフォーマンスを維持するには、業務量のバラつきをできる限りなくすことが大切です。
ここでは、業務平準化が重要視される理由について詳しく説明します。
業務の遅延を防ぐため
業務が一部の人に集中していたり、短期間にタスクが詰め込まれていたりすると、納期の遅延や進行の停滞が起こりやすくなります。
特にチームや部署をまたいだプロジェクトの場合、ひとつの工程が滞ることで、全体のスケジュールに大きな影響を及ぼします。
業務平準化を進めれば、リソース(人・時間)を適切に配分でき、各メンバーが計画的に作業を進めることが可能です。
属人化によるリスクを回避するため
特定の従業員にしかできない仕事が多くなると、その人の不在や退職により業務が滞る「属人化」のリスクが高まります。
加えて、業務負荷が特定の従業員に偏ることで、その人に過度なストレスや不満が蓄積され、モチベーションの低下や離職を招きかねません。
業務を平準化できれば、担当者を固定せず、複数の人が対応可能な体制を築けるようになります。
コストダウンを実現するため
業務平準化によって効率的に人材を活用できれば、間接的にコストダウンにもつながります。
例えば、無駄な残業や急な外注対応が減少すれば、その分の人件費や外注費を抑えることが可能です。
また、業務負荷が偏らずに進行すれば、ミスやトラブルも減少します。
その結果、サービス・品質が安定したり、重複作業を削減できたりといった形で無駄なコストを防げます。
業務平準化が進んでいない状態とは?
業務平準化がうまくいっていない職場では、いくつかの共通した問題が見られます。問題を放置すると、チームの生産性が下がるだけでなく、働く人の不満やストレスも高まるため、早期対処が必要です。
ここでは、業務平準化が進んでいない状態について解説します。
メンバーの作業量にバラつきがある
業務平準化ができていない職場では、チーム内で作業量に大きな差がある状況がよく見られます。
例えば、常に多忙なメンバーと、比較的余裕のあるメンバーが同じチームにいるようなケースです。この状態が続くと、負荷の大きいメンバーのモチベーションが低下したり、体調を崩してしまったりするリスクが高まります。
一方で、余裕のあるメンバーの能力を十分に活かしきれておらず、組織全体のパフォーマンスが最大限に発揮できているとはいえません。
時期によって作業量に差が出る
業務量が繁忙期と閑散期で極端に変動する場合も、業務平準化が十分に行われていない可能性があります。
例えば、年度末やイベント前のみに作業が集中し、それ以外の期間は手が空いてしまうケースです。
このように業務量に大きな波のある働き方では、短期間に多くのリソースを投入する必要が生じるため、急な残業や応援要員の手配が発生しやすくなります。
その結果、人件費の増加や作業ミスが起こる原因にもなります。
業務が属人化している
「この仕事は○○さんにしかわからない」という状況は、業務が属人化している典型例です。
このような状態では、業務のやり方がマニュアル化されておらず、ノウハウや判断基準が個人の経験に依存しています。そのため、同じ作業でも担当者によって作業時間や仕上がりにバラつきが生じ、結果として熟練した担当者へ業務が集中しやすくなります。
また、属人化した業務はブラックボックス化しやすく、業務改善や効率化の検討も難しくなります。
引き継ぎの際も、口頭での説明に頼ることが多く、新任者が一人前になるまでに長期間を要するという問題もあります。
業務平準化を進めるための具体的なステップ

業務平準化を実現するには、現状を正しく把握し、優先度を見極めた上で仕組みやツールを整えていく必要があります。
ここでは、業務平準化をスムーズに進めていくための6つのステップを紹介します。
【STEP1】業務を可視化する
最初のステップは「業務を可視化」することです。チームや部署内で「誰がどの業務を、いつ、どれだけの量、どれくらいの頻度で行っているのか」を一覧にまとめて把握しましょう。
業務を可視化することで、偏りや無駄が見えてきます。Excelや業務管理ツールを使って視覚的に整理すると、他のメンバーとも情報を共有しやすくなります。
【STEP2】平準化すべき業務に優先順位をつける
業務の可視化ができたら、次は「どの業務から平準化するか」を決めましょう。すべての業務を一度に変えようとすると、混乱を招くだけでなく、従業員の反発やストレスの原因にもなります。
まずは負荷が偏っていたり、属人化していたりする「優先度の高い業務」から改善を始めましょう。
例えば、「毎月末に一人だけが残業して処理している作業」などがあれば、業務平準化の対象として適しています。業務平準化は長期的な取り組みであるため、段階を踏みながら、無理なく浸透させていきましょう。
【STEP3】業務フローやマニュアルを見直す
平準化を進める上で欠かせないのが、業務のやり方を整えることです。業務フローがあいまいだったり、マニュアルが古かったりすると、同じ作業でも人によって進め方が異なり、作業時間や品質に差が出てしまいます。その結果、仕事が偏りやすくなります。
誰が担当してもスムーズに作業できるように、手順を明文化し、業務マニュアルとしてまとめましょう。
また、定期的に中身を見直し、現場の声を反映させることも重要です。全員が同じ基準で作業できる仕組みを整えることで、自然と平準化が進みます。
【STEP4】ITツールの活用を検討する
作業効率を上げ、誰でも同じように業務をこなせる環境をつくるには、ITツールの活用も有効です。
例えば、クラウドFAXやOCR(文字認識技術)を使えば、紙の書類を効率的にデータ化できます。また、タスク管理ツールを導入すれば、業務の進捗や担当状況が一目でわかるようになります。
さらに、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を使えば、定型的な作業を自動化し、人の手を減らすことも可能です。
ITツールの活用は、業務のバラつきを減らすだけでなく、作業時間の短縮や人的ミスの削減にもつながります。
【STEP5】業務の役割分担を最適化する
業務平準化の効果を高めるには、チーム内の役割分担を見直すことも重要です。管理者やチームリーダーが中心となり、各メンバーの得意分野やスキル、負荷状況を踏まえて業務分担表を作成し、全員で共有しましょう。
明確な分担があることで、責任範囲がはっきりし、仕事の偏りが起こりにくくなります。
また、メンバー間で業務のカバーができるよう、業務のローテーションやクロストレーニング(複数の業務をこなせるよう訓練すること)を取り入れることも有効です。
公平で柔軟な分担体制を整えることは、チーム全体の働きやすさと生産性の向上につながります。
【STEP6】定期的に見直しをする
業務平準化は実施して終わりではなく、継続的に効果を出し続けることが大切です。
導入直後はうまくいっていた取り組みも、業務内容やメンバー構成が変われば効果が薄れることがあります。
そのため、月1回や四半期ごとなど、定期的に業務のバランスや負荷状況を見直すことが必要です。
実際に現場のメンバーからフィードバックを収集し、必要に応じて業務配分やフローを調整していきましょう。
FAX業務の平準化にはクラウドFAXが最適
FAX業務は、紙の出力や確認、手動での送受信といったアナログな作業が多く、作業者への依存度が高くなります。受発注業務は取り扱う枚数が多いので「FAXの注文書を見落としてしまった」「別の取引先に誤って送信してしまった」といったヒューマンエラーも起こりがちです。これでは、業務の平準化は難しくなってしまいます。
そうした課題を解決する手段として注目されているのがクラウドFAXです。クラウドFAXサービス「まいと~く Cloud」を活用すれば、FAXの送受信をメールのような感覚で一元管理できます。
FAXの閲覧、振り分け、共有といった操作もすべてクラウド上で完結するため、紙への出力も不要です。自宅や外出先からでもオフィスと同じようにFAX業務ができ、テレワークや出張時にも便利です。
FAX業務の効率化を検討している方は、ぜひ以下より詳細をご確認ください。
まとめ
業務平準化とは、業務量の偏りをなくし、誰もが無理なく業務をこなせる状態をつくることを指します。メンバーの負荷のバランスを整えることで、業務の遅延や属人化を防ぎ、生産性の向上やコスト削減にもつながります。
平準化を進めるには、まず業務を可視化して問題を洗い出し、優先順位をつけて段階的に改善を進めることがポイントです。
また、定期的に業務を見直し、働きやすく持続可能な環境を整えていくことも大切です。業務のバラつきをなくし、チーム全体で安定した成果を出せる体制づくりを目指していきましょう。
