受発注業務とは? 業務の流れと課題、改善の方法を紹介
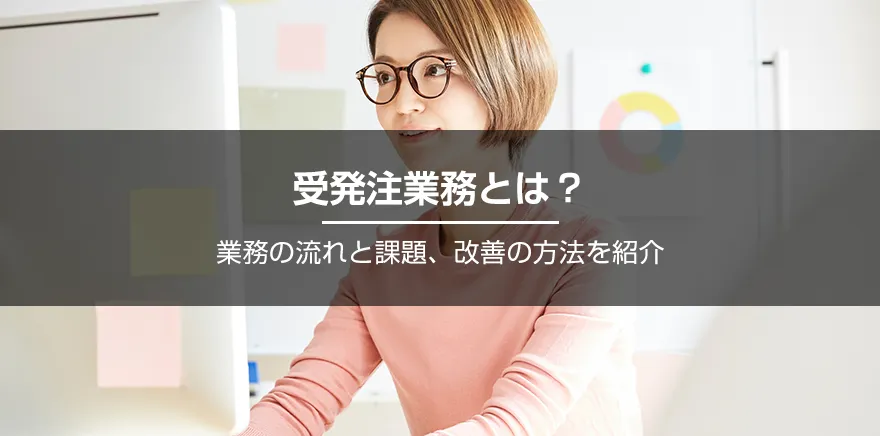
商品やサービスを売買する企業では、受発注業務が日常的に発生します。しかし、業務の流れが複雑で手作業が多いと、ミスや業務負荷の増加につながります。では、どうすれば受発注業務がスムーズになるのでしょうか。
今回は、受発注業務とは何かを解説し、業務の流れやよくある課題、効率化の方法について紹介します。業務改善を目指す企業の担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
受発注業務とは

受発注業務とは、自社が顧客から注文を受ける「受注」と、自社が取引先へ商品やサービスを発注する「発注」、この2つの業務を総称したものです。
製造業や卸売業、小売業などでは受発注業務が頻繁に発生するため、業務の正確性とスピードが求められます。
受注業務
受注業務とは、取引先や顧客から商品やサービスの提供を依頼されるプロセスのことです。例えば、企業が自社製品の購入依頼を受けることを「受注」と呼びます。
受注時には、注文内容の確認、納期の調整、在庫の確認、社内への製造・出荷指示など、様々な対応が必要です。
発注業務
発注業務は、原材料や仕入商品を他社から購入する業務です。例えば、小売店がメーカーから商品を仕入れる際の注文が「発注」です。
発注時には、見積取得、発注書の作成、納期の調整、納品確認などの作業が含まれます。
受発注業務の主な流れ

受発注業務は複数のプロセスに分かれており、各段階での正確な対応が業務の円滑な進行に直結します。ここでは、一般的な受発注業務の流れを発注側と受注側に分けて紹介します。
見積り
発注側
まず必要な商品やサービスについて仕入先に見積りを依頼します。提出された見積書をもとに、社内の決裁者へ提出し、金額や条件を確認・承認してもらいます。
受注側
顧客からの依頼に対して商品単価・納期・条件などを記載した見積書を作成して提出します。見積り段階での誤りや曖昧な条件は、後々のトラブルの原因となるため、丁寧な対応が求められます。
発注確定
発注側
見積りが承認された後は、正式な注文書を作成して仕入先へ送付します。この注文書は契約の証拠にもなる重要な書類であり、品目、数量、単価、納期などを正確に記載する必要があります。
受注側
注文書を受け取り次第、受注伝票や注文請負書を作成し、社内での出荷・生産準備に進みます。この段階では、双方の条件が明確に合意されているかを再確認し、認識のズレがないように注意が必要です。
発注側
納品された商品を受け取り、品質や数量に問題がないかを確認します。問題がなければ、商品は在庫として登録・保管します。
受注側
納期に間に合うように商品を出荷します。このとき、誤出荷や納品ミスを防ぐため、出荷指示書や納品書などの関連書類も一緒に手配します。
発注側
納品された商品に対して請求書を受け取り、内容を確認した上で、指定の期日までに代金を振り込みます。その際、振込後に領収書を受け取ります。
受注側
納品後速やかに請求書を発行し、正確な金額と支払期日を明記します。代金を受領し、領収書を発行します。
受発注業務における課題
受発注業務には様々な課題があり、放置すると業務効率の低下だけでなく、顧客との信頼関係にも悪影響を及ぼすおそれがあります。
ここでは、受発注業務における課題について解説します。
業務の煩雑化
受発注業務には、見積り、発注書・受注書のやり取り、納品管理、請求・支払いなど、多くの手順と文書が関係します。加えて、商品情報や価格、納期、契約条件といった詳細なデータを正確に管理しなければなりません。
そのため、手作業やExcelでの管理を続けていると、注文内容の取り違えや請求ミスといったヒューマンエラーが起こりやすくなります。
また、取引先や案件ごとに条件が異なるため、都度個別対応が求められ、業務がさらに複雑になります。
業務フローの属人化
業務の属人化とは、特定の担当者に業務のノウハウや手順が集中し、他のメンバーが対応できない状態を指します。
受発注業務でも、ベテラン従業員が独自の手順で処理しているケースが少なくありません。属人化が進むと、担当者が不在になった際に業務が滞るリスクが高まります。
また、業務の引き継ぎにも時間がかかり、全体の生産性が低下します。結果として、従業員一人ひとりの負担が重くなり、モチベーションが低下しかねません。
関係部門の連携不足
受発注業務は、営業・在庫管理・経理・販売管理といった複数の部門にまたがって進行します。そのため、部門間の連携が取れていないと、情報伝達の遅れや二重処理、処理漏れなどの問題が発生します。
例えば、営業部門が受注した内容が在庫管理部門に正確に伝わらなければ、納期遅延や在庫不足といったトラブルが起こるでしょう。
また、経理部門との連携が不十分であれば、請求金額の不一致や支払い遅延が発生する可能性もあります。
このような部門間の連携不足は、顧客満足度の低下につながります。
システム間の連携不足
多くの企業が受発注業務にシステムを導入していますが、販売管理システム、在庫管理システム、会計システムなどがバラバラに運用されているケースも少なくありません。
その結果、各システム間のデータ連携ができず、手入力による処理が増加します。手入力は作業負荷が高い上に、入力ミスのリスクも大きくなります。
特に金額や数量のミスは、顧客との信頼関係を損なうだけでなく、訂正のための工数やコストも発生するため注意が必要です。
受発注業務を改善するための方法

受発注業務における課題に対応し、業務全体を効率化するためには、計画的な改善策が必要です。
ここでは、その具体的な改善方法について解説します。
業務フローの可視化
受発注業務を効率化するには、現状の業務フローを可視化することが大切です。
具体的には、受注から納品・請求に至るまでの全プロセスを洗い出し、時間のかかっている工程やミスが発生しやすいポイントを把握する必要があります。
業務フローを可視化することで、ボトルネックや不要な手順を特定し、改善の優先順位を明確にできます。
また、可視化された業務フローは他の従業員にも共有しやすく、マニュアル化や教育に活用できる点もメリットです。業務フローが標準化されれば、属人化の防止にもつながります。
リソースの最適化
受発注業務の効率を高めるためには、人的リソースや時間の配分を見直し、最適化することが重要です。
例えば、受注処理に業務が集中している場合は、他の部門やメンバーと業務を分担することで負荷を軽減できます。
また、受発注業務では繁忙期と閑散期で業務量に大きな差が出ることもあるため、変動に対応できるよう人員配置を柔軟に見直すことが効果的です。
さらに、ルーティン業務については、自動化ツールの導入やサポートスタッフへの業務委託を検討してみると良いでしょう。
このように、限られたリソースを戦略的に活用すれば、業務全体の生産性を大幅に向上させることが可能です。
アウトソーシング
受発注業務の効率化には、業務の一部または全部を外部の専門業者に委託する方法もあります。
特に、定型的な受発注処理やデータ入力、請求業務などの定型業務は、アウトソーシングに最適です。
アウトソーシングの最大のメリットは、社内リソースをコア業務に集中できることです。これにより、従業員はより付加価値の高い業務に注力でき、企業全体の競争力向上につながります。
さらに、専門業者は豊富な経験とノウハウを持っているため、高い品質と正確性を維持しながら業務を遂行できます。加えて、繁忙期と閑散期に応じた柔軟な人員配置が可能になり、人件費の最適化も実現できます。
受発注システムの導入
受発注システムを導入し、紙ベースやExcelで行っていた受発注処理をデジタル化することで、注文入力、納期管理、請求書作成などの作業を自動化できます。その結果、人的ミスの削減と、作業時間の短縮が可能になります。
また、システム上で業務履歴を一元管理できるため、過去の取引内容や進捗状況の確認が容易になり、業務の透明性が向上する点もメリットです。
さらに、他の基幹システムと連携すれば、社内の情報共有がスムーズになり、部門間連携の課題も解消できます。
受発注業務の効率化には「まいと~く Cloud」が最適
受発注業務の効率化を目指してシステム導入を検討する企業が増えていますが、業界の慣習や取引先の都合により、依然としてFAXを利用せざるを得ないケースも少なくありません。
このような背景を踏まえ、FAXのクラウド化が新たな選択肢として注目されています。クラウドFAXサービス「まいと~く Cloud」は、従来の紙FAXの代わりにインターネットを通じてFAXを送受信できるサービスです。
FAXをメールのように扱えるため、受発注業務の効率化が大幅に進みます。受信したFAXはクラウド上で閲覧・検索・共有・振り分けが可能で、テレワーク環境でもオフィス同様の業務処理が実現できます。
また、Web API連携やCSV・PDF形式での出力機能など、基幹システムとの連携にも優れており、既存の業務フローに柔軟に対応可能です。FAXのクラウド化により、紙での管理が不要になり、属人化やミスの軽減、業務スピードの向上が見込めます。
さらに、OCRシステムを連携すれば、転記作業の自動化も可能となります。(FAXをOCRで電子化するメリット・デメリットについての記事はこちら)
FAX業務の効率化を検討している企業様は、ぜひ以下より詳細をご確認ください。
まとめ
受発注業務は、企業活動を支える重要なプロセスです。とはいえ、煩雑な業務フローや属人化、部門間の連携不足など、多くの課題を抱える企業も少なくありません。
これらの課題を解決するためにも、業務フローの可視化やリソースの最適化、アウトソーシングの活用、受発注システムの導入といった多角的なアプローチを検討してみてください。
