【法人向け】FAXの料金はいくらかかる? コストを抑える方法も解説
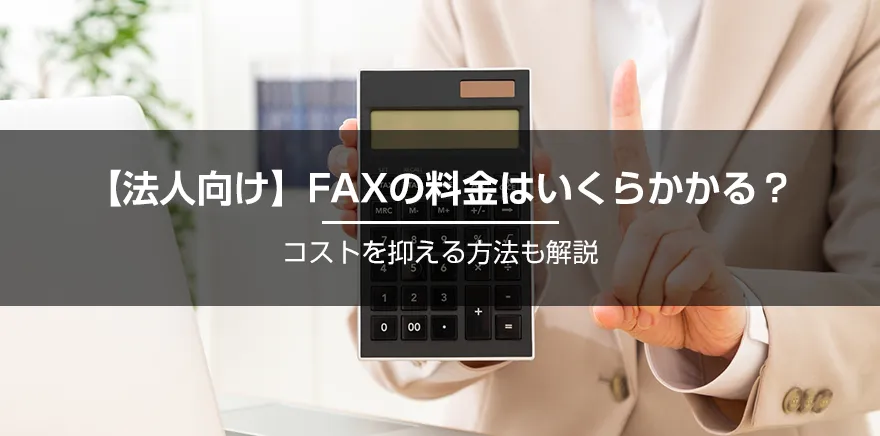
ビジネスで利用されるFAXには、送信料や印刷代、複合機の費用、回線費用など、想定以上に多くのコストが発生しています。こうした課題は、適切な対策を講じることで大幅に削減することが可能です。今回は、FAXの料金体系を詳しく解説するとともに、効果的なコスト削減方法をご紹介します。
FAXの料金はいくらかかる?

FAXの利用料金は送信料と受信料で構成されており、どちらの料金も利用するサービスや回線によって異なります。まずは、それぞれの料金体系を確認しましょう。
FAX送信時の場合
FAXの送信にかかる料金は、電話をかけるときと同様に通信料として発生します。
NTTのアナログ回線は通話時間に応じて課金される仕組みで、送信枚数やページの内容が料金に大きく影響します。クラウドFAX(インターネットFAX)はページ単位で課金されるため、サービスによっては月間100枚程度まで無料で利用できる場合もあります。
主なFAX回線、サービスの送信料の目安は次の通りです。
| 回線、サービス | 送信料(税込) |
|---|---|
| NTTのアナログ回線 | 3分あたり約9.35円(国内送信) |
| 光電話回線(ひかり電話) | 3分あたり約8.8円 |
| クラウドFAX(インターネットFAX) | ページ単位で課金 |
FAX受信時の場合
FAXの受信では、通信料が発生しません。ただし、複合機の場合は、受信したFAXを紙へ印刷する際に「カウンター料金」と呼ばれる印刷コストが発生します。
カウンター料金とは、複合機の導入時にメーカーや販売店と結ぶ「カウンター保守契約」に基づき、印刷枚数に応じて課金される料金です。そのため、FAXを受信しても紙に印刷しなければ、カウンター料金は発生しません。
また、この料金にはトナー代やメンテナンス費用なども含まれています。
印刷1枚あたりのカウンター料金は契約内容によって異なります。以下は一般的な料金目安です。
| 印刷タイプ | 1枚あたりの料金 |
|---|---|
| モノクロ | 2円~3円 |
| モノカラー | 5円~10円 |
| フルカラー | 15円~25円 |
なお、クラウドFAXは情報がデータとして保存されるため、FAXを確認する際に紙への印刷が不要です。基本的に、FAXの受信では追加料金は発生しません。
FAXの通信料以外にかかるコスト

FAXにかかる費用は、送信料や受信料だけではありません。通信費以外にも複合機の送受信で発生する費用や回線の固定費が発生します。それぞれのコストについて詳しく見ていきましょう。
複合機の費用
複合機の購入費用は、新品か中古か、カラーかモノクロか、さらに機能性や印刷速度などによって価格帯に幅があります。
新品の相場は、カラー複合機で120万円以上、モノクロ複合機で70万円以上です。中古の場合は、5万円~30万円台で購入できる機種もあります。
また、リース契約の場合は毎月のリース料が発生します。そのほか、保守費用やトナー代、用紙代なども、複合機の利用で想定されるランニングコストです。
電話、インターネット回線の固定費
複合機でFAXを利用するには、電話回線またはインターネット回線を契約し、月額利用料を支払う必要があります。これは先述の通信料とは別に発生する料金です。
なお、NTTのアナログ回線は、2024年1月よりインターネット回線へ順次移行しています。既存サービスは継続して利用が可能です。代替となる光回線のひかり電話は、月額550円で利用できます。
FAXにかかる料金を抑える方法

ここでは、日常業務の見直しや工夫でFAXにかかる料金を削減する方法について解説します。
アナログ回線から光回線に切り替える
アナログ回線を利用している場合は、光回線への切り替えによりFAXの送信料を抑えられます。
光回線のFAX送信料は、全国一律の「3分あたり約8.8円(税込)」です。アナログ回線の「3分あたり約9.35円(税込)」と比較して、より安価な料金でFAXを送信できます。
なお、FAXと光回線の接続の仕組みは、基本的にアナログ回線と同様です。アナログ回線で利用していた既存の複合機を継続して使用できるため、設備投資に大きなコストが発生する心配はありません。
自動印刷の設定をやめる
複合機の自動印刷機能がオンになっている場合は、解除しておきましょう。
自動印刷設定は、受信したFAXをすべて自動で印刷する機能です。自動印刷機能をオフにして必要なFAXのみを選択して印刷することにより、カウンター料金やトナー代、用紙代などのコストを抑えられます。
さらに、複合機には次のような機能を搭載した機種もあり、印刷前にFAX内容を確認できます。
- プレビュー機能:複合機のディスプレイで受信したFAXを確認する
- PC-FAX機能:PCと複合機を接続し、PCの画面上でFAXの確認、送信をする
これらの機能を活用することで、不要な印刷を減らせます。
契約内容を確認する
リース契約の場合、業者によって月額料金やカウンター料金の設定が異なります。契約前に内容を十分確認することに加え、定期的に契約内容を見直すと良いでしょう。
例えば、カウンター料金がより安価なリース業者と契約することで、ランニングコストの削減につながる場合も少なくありません。枚数が多い場合は、リース会社に値下げを交渉できる可能性もあります。
クラウドFAXを活用する
クラウドFAXを導入すれば、受信したFAXはデータとして保存されます。そのため、従来のFAXで発生していた受信時の印刷が不要となり、印刷コストを大幅に削減できます。たとえ多くの枚数を受信したとしても、カウンター料金は発生しません。
クラウドFAXとは、インターネット回線を介してFAXを利用するサービスです。手元のPCやスマートフォンを使ってFAXの確認、送信が簡単に行えます。送受信枚数が少ない場合でも、無料枠が設定されたサービスを利用すればコストを抑えられます。
FAXのコスト削減にはクラウドFAXがお勧め! 主なメリットとは
FAXにかかる料金を抑える方法のうち、クラウドFAXは特に費用対効果が高い解決策といえます。従来の複合機を使用したFAXからクラウドFAXへ移行することで、次のようなメリットが得られます。
ペーパーレス化
クラウドFAXの大きなメリットは、FAXの確認、送信から保存、管理までデジタルデータで行うため、用紙代やトナー代などの印刷コストを抑えられる点です。
FAXが届いた際は内容を確認した上で、必要なFAXのみを紙へ印刷すれば済みます。
FAXの送信についても、PC上で作成した文書をわざわざ印刷してから送信する必要はなく、データのまま直接デバイス上から送信できるため、紙を使用しません。
さらに、複合機を置く必要がないため、メンテナンスの手間が発生しません。従来の紙媒体のFAXでは必要となる書類の保管場所も不要です。
DX化による働き方改革
従来のFAX業務には、送信前の連絡や送り状の作成のほか、大量の書類は送信不可などのマナーがあります。これらは送信先への必要な配慮ではあるものの、迅速な業務の遂行を妨げる側面もありました。
クラウドFAXを導入すれば、こうした従来の制約を解消し、紙媒体で行っていたFAX業務をデジタルデータで完結できます。送信前の煩雑な手続きが簡略化され、データの迅速な共有が可能となることで、業務効率の向上や企業のDX化を大きく促進する可能性があります。
また、インターネット環境とデバイスさえあればFAXを利用できることから、出張先やテレワークなど、オフィス以外の場所での柔軟な働き方を可能にする点もメリットです。
セキュリティ強化
従来のFAXでは、受信した用紙が複合機周辺に放置されることで、機密情報や個人情報が悪意のある第三者に閲覧されたり、外部に持ち出されたりするリスクがありました。
一方、クラウドFAXでは、FAXをデジタルデータとして保存、管理できるため、このような情報漏洩の心配はありません。
さらに、多くのサービスでは、情報漏洩やデータ改ざんなどのリスクを低減するため、以下のようなセキュリティ機能が搭載されています。
- アクセス権限設定:部署や役職などで閲覧や編集、送信などの権限を細かく設定する
- 証跡管理機能:通信の記録を管理することでデータの改ざんを抑止する
クラウドFAXなら「まいと~く Cloud」が最適
FAXにかかるコストを削減するために、クラウドFAXへの移行を検討している方は、「まいと~く Cloud」をご検討ください。
「まいと~く Cloud」は、FAXの確認、送信をメール感覚で一元管理できるクラウドFAXです。FAXの閲覧、振り分け、共有がすべてクラウド上で行えるため、出張先やテレワークなどでもオフィス環境と同じようにFAX業務に従事できます。
そのほか、帳票システムで作成した納品書の自動送信、受信した注文書のOCRへの自動受け渡しなど、基幹業務システムとの連携を実現できる点も魅力です。初期費用が発生せず、回線やサーバーの導入も必要ありません。
FAX業務のコスト削減に関心のあるご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
従来のFAXを利用する際には、通信料だけでなく、複合機の導入費用や回線費用、印刷代などがかかります。
コスト削減策として、アナログ回線から光回線への切り替えや、自動印刷設定の解除なども有効ですが、中でも費用対効果の高い方法がクラウドFAXの導入です。コスト削減だけでなく、ペーパーレス化やDX化、セキュリティ強化などのメリットも期待できます。
「FAX業務の経費を削減したい」「コストパフォーマンスの高いFAX運用を実現したい」という企業様は、ぜひ「まいと~く Cloud」をご検討ください。
