FAXで注文書を送るときのマナーと課題|効率化のための代替方法
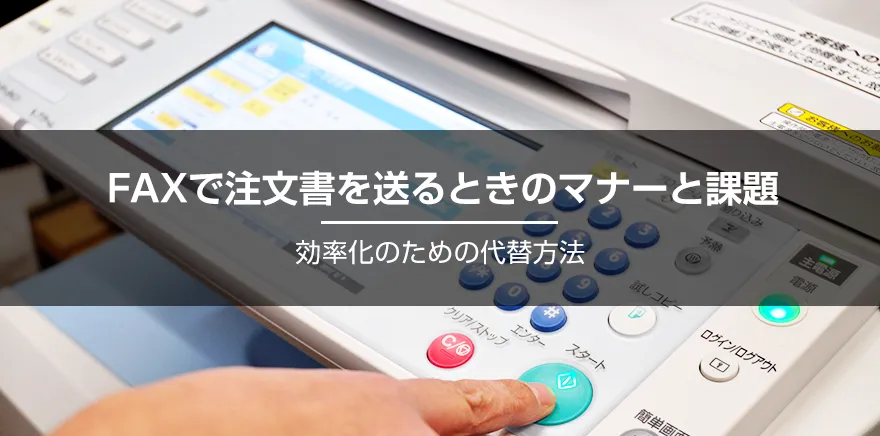
メールやチャットでのやり取りが普及した現代でも、「注文書はFAXで」といわれるケースは少なくありません。特に若手、新入従業員の中には、これまでFAXを利用したことがなく送信時のマナー に不安を覚える方もいるのではないでしょうか。
また、FAXでのやり取りにはいくつかの課題もあるため、他に効率の良い方法はないかと考えている方もいるかもしれません。
そこで今回は、FAXで注文書を送る際のマナーや、業務効率化に役立つ代替手段などについて解説します。
FAXで注文書を送る際のマナー

電話やメールにマナーがあるように、FAXで注文書を送るときにも押さえておきたいマナーがあります。信頼できる企業、担当者という印象を与えるためにも、FAX送信時の基本のマナーを覚えておきましょう。
送付状をつける
注文書に限らず、顧客や取引先にFAXを送信する際には「送付状」を添えるのが一般的です。注文書とは別に送付状を用意し、「①送付状」「②注文書」の順に送りましょう。
また、書類の順番を把握できるように、各書類にページ番号を記載することも重要です。これは、書類の抜けがないかを確認する際にも役立ちます。
誤送信には注意する
FAXの送り先を間違えると商品を注文できないだけでなく、情報漏洩につながります。注文書を送信する前に送り先のFAX番号を複数回確認し、誤送信が起こらないようにしましょう。
機密文書・親展書類は送らない
機密情報や個人情報が書かれた書類、親展書類などをFAXで送るのは避けましょう。FAXを受け取るのが担当者であるとは限らず、第三者が内容を見てしまうリスクがあるためです。
どうしても社内情報や個人情報を記載しなくてはならない場合は記載内容に注意し、必要な情報以外は書かないようにしましょう。
細かい文字や図は避ける
FAXで細かい文字や図が入った書類を送ると、潰れてしまって読み取れなくなることがあります。相手先のFAXの性能が判断できないのであれば、細かい文字や図は避けて、見やすく大きな文字にするよう心がけましょう。
また、カラーの書類も正常に送れない場合があります。FAXで送るのは白黒の書類のみにし、カラーの書類は郵送やメールなどで送りましょう。
- あわせて読みたい
FAXで注文書を送る際の課題

FAXで受発注を行うと、様々な課題が生じる場合があります。特に業務に大きな影響を与える可能性が高い課題を4つ解説します。
送受信に手間がかかる
FAXで受発注を行う場合、紙の注文書に手書きで必要事項を書くかパソコンで作成した書類を印刷する必要があり、送信完了までに手間がかかります。
また、FAXはオフィスに設置されたFAX機や複合機などで受信するため、相手先の担当者が書類を確認するまでに時間がかかる場合もあります。もし担当者が在宅勤務中だったり出張中だったりすると、アクションが返ってくるまでに数日かかるかもしれません。
また、相手先の営業時間外に送った場合、次の営業日まで書類が放置されるため、リアルタイムでの情報共有が難しくなります。
送信ミスが起こる
FAXは送信時にFAX番号を入力するか、登録している番号から選択して送るため、メールやチャットなどと比べて送信ミスが発生しやすいという課題もあります。
うっかりFAX番号を押し間違えたり、社名や番号を間違えて登録したりした結果、別の顧客や取引先に書類を送ってしまいます。送信先を間違えると、第三者に情報が漏れる恐れがあるため、注意が必要です。
また、相手先の担当者以外の人がFAXを受け取り、情報漏洩につながるリスクもあります。
維持コストがかかる
FAXを送受信するには、FAX機や複合機のほかにインクやトナー、印刷用紙なども用意する必要があり維持コストがかかります。機器をリースしている場合は、月々のレンタル料もかさむでしょう。
リモートワークに対応できない
FAXはオフィスに設置しているFAX機や複合機から送信します。そのため、FAXを送信するにはオフィスに出向く必要があり、リモートワークやテレワークができないという課題もあります。
また、紙に印刷して送信しなくてはならないため、担当者が出張や在宅勤務などで離れた場所にいるとスムーズに情報共有できないのもデメリットです。
FAX注文に代わる方法

先述の通り、FAXで注文書を送るのは手間がかかる上に情報漏洩のリスクがある、維持コストがかさむなどのデメリットがあります。
これらのデメリットを軽減し、業務効率を上げるには、FAX注文を廃止して代替手段を導入する必要があります。ここではFAX注文に代わるお勧めの方法を3つ紹介します。どの方法が自社に合うかを考えてみましょう。
クラウドFAX
クラウドFAXとは、インターネットを利用してFAXを送受信できるサービスです。書類をデータ化してクラウド上に保存することで、パソコンやスマートフォン、タブレットなどの端末から簡単にFAXを送信できます。
相手先から届いたFAXもデータ化されてクラウドに保存されるため、管理が簡単です。また、クラウド上でのやり取りとなるためFAX機や複合機、固定電話回線などを用意する必要がなく、サーバーも不要です。
相手先が固定電話回線で紙のFAXを受信している場合は、相手の環境に適した形式で書類が送信されるため、相手先にクラウドFAXを導入してもらう必要はありません。
EDI(インターネットEDI)
EDI(Electronic Data Interchange)とは、企業同士を専用回線でつないで電子データをやり取りできるシステムです。書類を手入力することがないため、送信までの時間を短縮するのに役立ちます。また、専用回線を利用するため誤送信も防止可能です。
BtoB-EC
BtoB-ECとは、企業同士で商品やサービスを売買するためのECサイトシステムです。個人がネットショップで買い物するように、注文したい商品やサービスをECサイトから注文できます。もちろん決済や配送などの手配も可能です。
FAX注文をスムーズにするなら「まいと~く Cloud」
様々な代替手段がありますが、導入の手軽さなどを考えるとクラウドFAXがお勧めです。しかし、どのクラウドFAXを導入すべきか悩むこともあるでしょう。
そのようなときは、ぜひ「まいと~く Cloud」をご検討ください。「まいと~く Cloud」なら、FAXの送受信をメール感覚で一元管理できます。紙に印刷する必要がなく、すべてWebブラウザー上で確認できるため、ペーパーレス化推進にも役立つでしょう。
また、FAXの閲覧・振り分け・共有をすべてクラウド上で完了できるため、オフィスに出向かなくてもFAXを送受信できるのもメリットです。業務システムと連携すれば、FAX業務の自動化も実現できます。
原稿編集が可能で、注文書や見積書に任意のテキストやハンコの画像などを簡単に挿入できるのも魅力です。さらに有料オプションとして、誤送信防止機能などのセキュリティ機能も搭載されているほか、運用支援サービスも利用できます。
14日間の無料トライアルも実施しているため、FAX注文の効率化を検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
現在もFAXで注文書を受け付けている企業は多く存在しますが、FAXの送受信は手間も時間もかかるため業務効率を低下させる原因にもなり得ます。
また、誤送信や文字が潰れて読めないなどの問題も起こりやすいため、可能であれば代替手段を探すことをお勧めします。今回紹介した内容を参考に、どの方法が自社に最適かを検討してみましょう。
